
記事の執筆は情報収集が大事。
これはもうあたりまえの話です。
あたりまえすぎて何を今さら?って思いますよね。
アフィリエイト記事を書くなら、その前にリサーチ。
これをやらないと、餡子の入ってないたい焼きみたいなスカスカの記事になります。
そんなもん、誰が食うか!って話です。
ただ、この情報収集が意外と難しい。
今はネットでいくらでも情報を得られますが、集めればいいというもんじゃない。
特に、ネタを決めて記事を書くときにやる情報収集は、情報の寄せ集めになりがちです。
その結果、どこかで読んだことがあるようなリライト記事になってしまう。
腐った食材で料理を作ると、まずいだけじゃなく、お腹をこわします。
そんな料理は二度と食べてもらえません。
これを避けてオリジナリティーのある記事を書くためには、日頃から情報のインプット作業をしておく必要があります。
そして、記事を書くときに使う。
そうすれば、情報元の記事にはない別の視点や言い回しを使って書くことができます。
冷凍庫に保存しておいた食材を取り出して、料理に使うような感じですね。
材料を的確に選べば、少々作り方が下手でもおいしく食べられます。
記事も同じです。
文章力が不足していても、読みたくなるような情報がきちんと入っていれば、読んでもらえる記事を書くことができるのです。
この記事の目次
よく文章を書くことは0を1にする作業だという人がいます。
しかし、これは間違いです。
文章を書くことは100を1にすることです。
つまり、インプット100、アウトプット1。
これが文章を書くうえでの理想形です。
人気作家はひとつの作品を書くために、取材に膨大な時間を宛てます。
しかし、実際に作品に反映されるのは、1割くらい。
100調べた中で、出すのはたった1。
人を惹きつける文章というのは、こうした過程を経て生み出されるものなのです。
とはいえ、100のインプットなんて言われると、尻込みしていますよね。
さすがにそこまではやれない。
というのが、正直な感想ではないでしょうか?
そんなにいっぱい情報を集められないよ。
それに時間ばかりかかって書く時間がなくなっちゃう。
おしゃるとおり。
では、どうすればいいのか?
インプットを増やすには隙間時間を使うのがおすすめです。
パソコンの前にいる時間は、基本的には記事執筆の時間に充てるようにしてください。
そこで、紹介したいのが……

インプットを増やす一番の方法は、とにかくメモを取ることです。
気になったこと、思いついたこと、心に残ったことをその場でメモする。
電車での移動中でも、食事の最中でも、寝る前でも……
いつでもどこでもメモを取る習慣をつけることです。
たとえば、スマホなら手書きや音声入力もできるメモアプリがたくさんあります。
電車の週刊誌の中吊りをカメラで撮るというのもありです。
常にアンテナを張っておくことで、インプット力は格段に上がります。
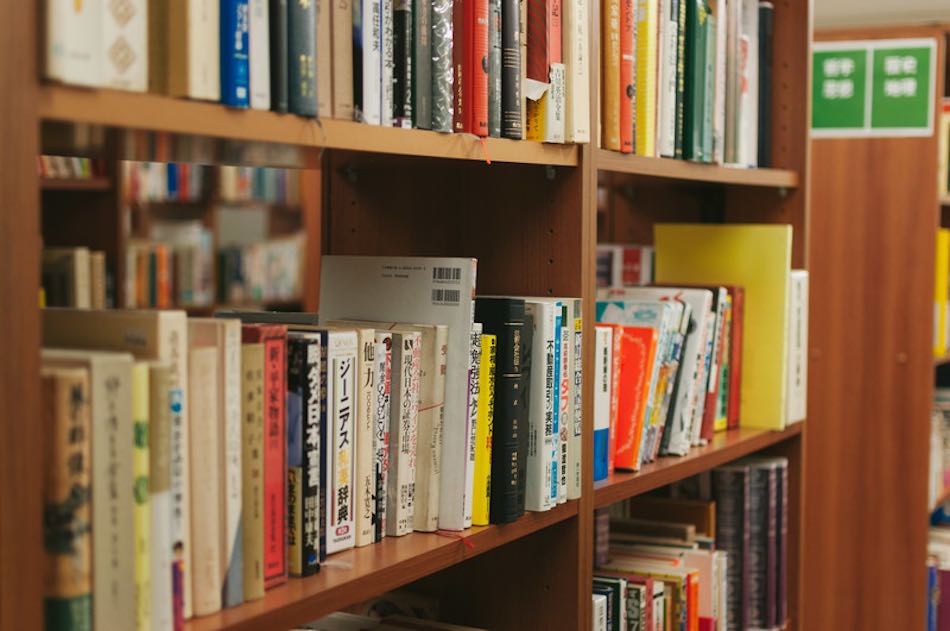
空いた時間があるときは本屋に立ち寄りましょう。
本屋は情報の宝庫です。
タイトルを見て回るだけでも、インプット作業になります。
本のタイトルというのは、売上の鍵を握る大きな要素。
そのため、どれも練られたタイトルになっています。
記事タイトルを考えるうえで、とても参考になります。
いいな、と思った本のタイトルを見つけたら、
手に取って目次を見てみるのも役に立ちます。
タイトルの良い本は目次も良いものです。
ぜひ参考にしましょう。
本屋に行く時間がなければ、スマホで代替することもできます。
たとえば、dマガジンは月400円で240誌以上の雑誌が読み放題のサービスですが、これで雑誌の表紙を斜め読みするだけでも、情報収集できます。

インプット力を高めるには人の話を聞くことも有効な方法です。
人間は目よりも耳から得た情報の方が頭に残りやすいと言われています。
耳は真っ暗闇でも音を感知できます。
人間の耳が発達したのは、身の危険を守るためで、そうした進化の歴史からみても、「目からの記憶」より「耳からの記憶」のほうが印象に残るのです。
だから人の話は積極的に聞くようにしましょう。
もし、なかなか聞く機会がないと言う場合は、YouTubeがおすすめです。
YouTubeには、役に立つセミナー動画などが数多くアップされているので、探して観てみるといいでしょう。
そうすれば、目と耳両方を使って情報収集ができます。
インプットが「読む」だとすれば、アウトプットは「書く」です。
では、記事を書く際に、インプットをアウトプットに活かすにはどうすればいいのか?
わかりやすくするために料理にたとえます。
インプットは食材、アウトプットは料理。
おいしい料理を作るには、良い食材を上手に使うこと。
食材は切り方、調理の仕方、調味料の加え方で味が決まります。
そして、盛り付け方もおいしさを目で味わうための重要な技術です。
これらが合わさって、お客さんは満足してくれるのです。
文章も然り。
インプットした情報や知識を上手に使ってアウトプットすることで、読者に満足してもらうような記事になるのです。
えっ、なんとなくはわかるけど、具体的なやり方がわからない?
わかりました。では、より詳しく解説します。
読みやすくて面白い記事というのは、「たとえ」が上手です。
「たとえ」とは、言いたいことをわかりやすい事象に言い換えて表現する手法。
レトリックとも呼ばれます。
テレビでよく芸人が笑いを取るときに使いますね。
たとえば、フットボールアワーの後藤輝基。
テレビ界で彼は「たとえツッコミ」の名手と言われています。
こんな感じです。
南海キャンディーズのしずちゃんに対して、
「四捨五入したらオスですよ!」
男っぽいというのを「四捨五入」という想像もしなかった言葉でたとえて笑いを取る。
この意外性が場をなごませ、トークに厚みを出します。
僕はこの記事の冒頭で、「中身のないスカスカの記事」というのをこんなふうに書きました。
「餡子の入ってないたい焼きみたい。そんなもん、誰が食うか!」
これが「たとえを使う」ということです。
僕は日頃、こうした「たとえ」をストックしていて、記事に使うようにしています。
これは僕にとっては、重要なインプット作業でもあるのです。
料理で言えば、スパイスのようなものですね。
「へえ〜」と思ってもらうための雑学知識を記事にまぶすのも効果的です。
たとえば、こんな一口豆知識。
「三島由紀夫の愛読書は国語辞典」
これは以前本屋で立ち読みしているときに見つけて、メモしたもの。
今回の記事で紹介した「インプット」に関する説明でも使えます。
「三島由紀夫の愛読書は国語辞典だったそうです。
あれほどの大作家でもどん欲に言葉をインプットしていたんですね」
こんな感じで、1エピソード加えれば、読み手に満足を与えることができます。
こちらは料理で言えば、付け合わせを一品加える感じです。
これは料理で言えば、メインメニューの味そのものです。
見栄えはいいんだけど、食べてみると味が物足りないということがありますね。
これは何かが欠けているからです。
記事で言えば、知りたいことに完全に答えられていないということ。
疑問が残る状態です。
それを避けるためには、読者に疑問を抱かせない記事を書くこと。
記事を書くときは何度も読み返して、少しでも疑問が生じたら、その場でリサーチする。
そして、その部分をわかりやすく説明する。
これを徹底することで、あなたの記事は一気に質の高いものに変わります。
読者は疑問を持つと、すぐにページを閉じて、他のサイトへ行ってしまいます。
逆に、読者は疑問が完全に解消されて満足すれば、他の記事も読んでみようという気になります。
グーグルの検索エンジンは、滞在時間の長いブログを高評価し、上位表示させる仕組みになっています。
さらに、疑問が解決されれば、そばにある広告をクリックしてくれる確率も高まります。
つまり、最後まで読んでもらえる記事を書くことが収入を増やす一番の方法なのです。
検索エンジンは日々進化しています。
どんなにライバルのいないキーワードを見つけられたとしても、中身がおそまつだと、その記事はいつまで経っても上位表示されなくなってきています。
ライバルに勝つためには、記事の中身を充実させること。
そして、読者に最後まで読んでもらうこと。
これを実現するためには、日頃のインプット作業と妥協のないアウトプット作業がとても大切なのです。
餡子の入ってないたい焼きは誰も食べてくれません。
そのことをしっかり胸に刻んで、記事を書いてみてください。
コメントフォーム